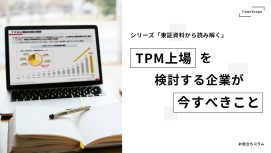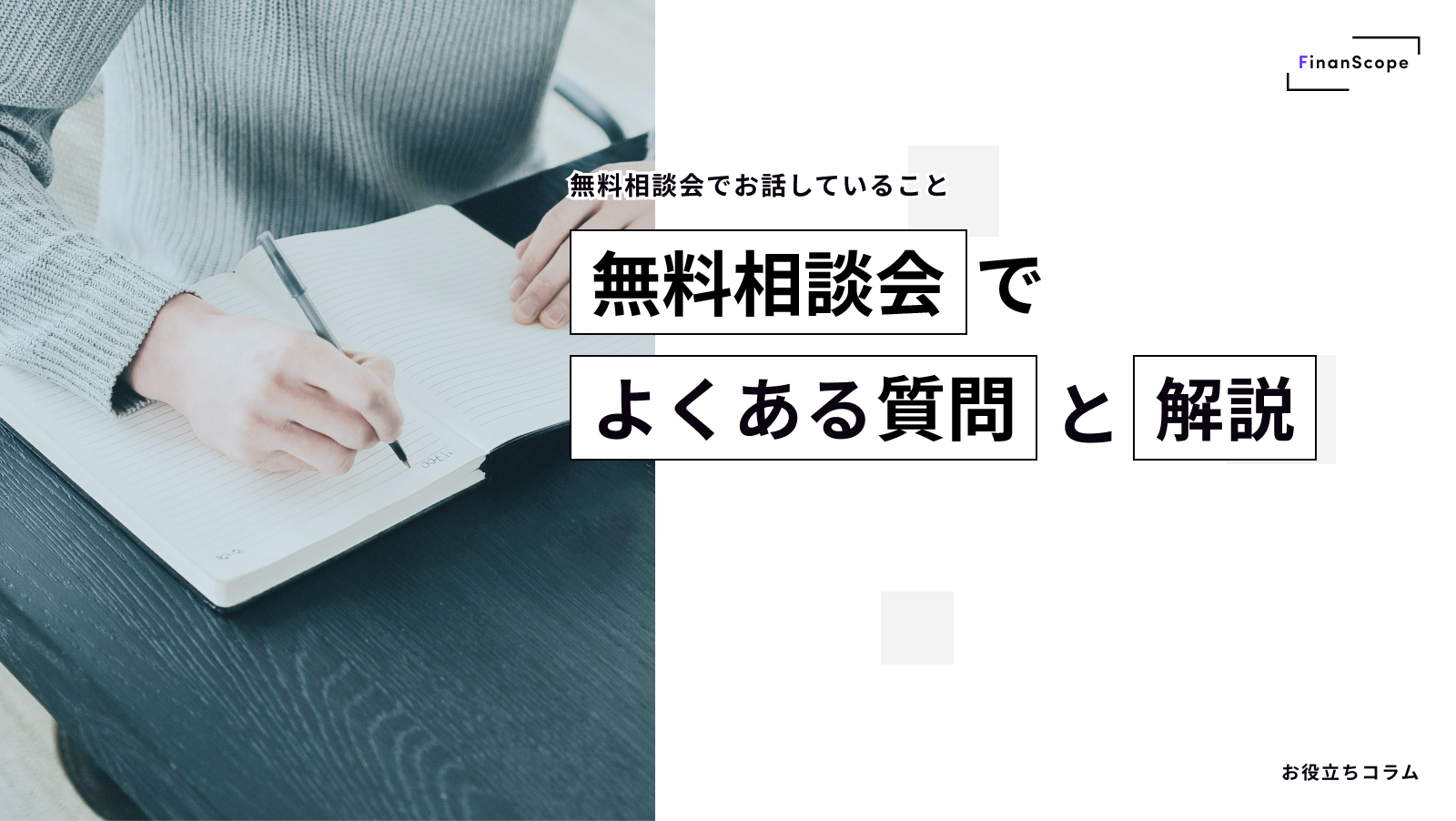
デジタルキューブ 取締役 / 公認会計士・税理士 和田 拓馬
上場準備クラウド「FinanScope」では、上場を検討している企業向けの無料相談会を実施しています。この相談会では、上場準備における様々な疑問や不安に対して、私たちの経験を踏まえたアドバイスを提供しています。今回は相談会でよく寄せられる質問や、私たちがお伝えしているアドバイスの一部をご紹介します。
目次
1. 上場準備を始める前に知っておきたいこと
・上場準備はいつから始めるべきですか?
相談会で頻繁に受ける質問の一つが、上場準備の適切な開始時期についてです。この問いに対する回答は、目指す市場によって大きく異なります。
TOKYO PRO Market (TPM) の場合
TPMを目指す場合は、上場までの期間として2年〜2年半程度を見込んでおくと良いでしょう。比較的短期間で上場が可能な点が TPM のメリットのひとつですが、それでも社内体制の整備には一定の時間が必要です。
一般市場(東証グロース市場など)の場合
一般市場を目指す場合は、3年〜3年半以上の準備期間を見込むことをお勧めしています。内部統制やガバナンス体制の整備、開示体制の確立など、より広範な準備が必要になります。
・どの程度の業績があれば上場準備を始められますか?
「営業利益がどれくらいあると上場準備を始めてもいいのか」というご質問も頻繁にいただきます。
目安としての数字
実務的な観点からは、営業利益3,000万円程度を一つの目安として考えるとよいでしょう。これは準備段階での外部コスト(監査法人費用、証券会社費用など)やシステム投資、人材採用などに必要な資金を考慮した数字です。
ただし、これはあくまで目安であり、業種や成長率によって大きく異なります。例えば、FinTech や SaaS など高成長が見込めるビジネスモデルであれば、一時的に赤字でも成長投資として評価されるケースもあります。
成長性と持続可能性
上場市場では、単年度の利益よりも、持続可能な成長が見込めるかどうかが評価されます。特に TPM においては、形式基準(売上高や利益などの数値基準)がないため、持続的な成長モデルが確立できていることがより重要になります。
・どの市場を目指すべきでしょうか?
上場を検討する際、多くの経営者が「自社にはどの市場が適しているのか」と迷われます。この問いに対しては、企業の特性や目標に応じた選択が重要です。
TOKYO PRO Market(TPM)が適している企業
- 堅実な成長を目指す中堅・中小企業
- 地方に拠点を置く企業
- 資金調達よりも、上場による信用力向上やガバナンス体制の確立を重視する企業
- 将来的にスタンダード市場などへのステップアップを視野に入れている企業
東証グロース市場が適している企業
- 高成長を見込むスタートアップ企業
- 大規模な資金調達が必要な企業
- 外部株主に一定以上の株式売却機会を用意する必要がある企業
選択は企業の成長戦略によって大きく異なりますので、まずは自社の将来ビジョンと照らし合わせて検討することをお勧めしています。
2. 管理部門の体制構築について
・管理部メンバーの採用順序や適性について
上場準備における重要な課題の一つが、管理部門の体制構築です。「どのような順序で人材を採用すべきか」「どんな適性が必要か」といった疑問は、多くの企業に共通する悩みです。
最初に採用すべき人材
上場準備の初期段階では、まず管理部門の責任者(CFO や管理部長)の採用・選任が最も重要です。この人材が上場準備のプロジェクトリーダーとなり、必要な体制構築を進めていくことになります。
次に重要なのは、経理実務のリーダーとなる人材です。月次決算や予実管理、開示書類の作成など、経理財務面での対応は上場準備の中核となります。
段階的な体制構築
その後は以下のような順序で体制を拡充していくことが一般的です。
- 経理・財務担当者(月次決算、予実管理)
- 総務・法務担当者(規程整備、契約管理)
- 人事・労務担当者(人事制度、労務管理)
- IR 担当者(投資家対応、開示準備)
ただし、企業規模や業種によって必要な体制は異なります。すべての機能を自社で持つ必要はなく、特に初期段階では一人が複数の役割を担ったり、外部リソースを活用したりする柔軟なアプローチも有効です。
・内部監査担当者の採用は必要ですか?
「内部監査の担当者を採用する必要があるか」というご質問も多くいただきます。限られたリソースの中で、専任の内部監査担当者を置くべきかどうかは難しい判断となります。
アウトソーシングの活用
結論から申し上げると、内部監査機能はアウトソーシングでかなり補うことが可能です。特に上場準備段階では、専門的な知見を持つ外部の専門家のサポートを受けることで、効率的かつ有効な内部監査体制を構築できます。
内部監査機能の段階的整備
初期段階では外部リソースを活用しつつ、上場後に徐々に内製化を進めていくアプローチも有効です。この場合、まずは兼務担当者を置き、段階的に専任の内部監査担当者を育成していく方法が考えられます。
・外部専門家との連携はどのように進めるべきですか?
上場準備では、社内体制の整備と並行して、外部専門家との関係構築が鍵となります。特に地方企業の場合、この連携をどう効率的に進めるかは重要な課題です。
専門家チームの組成時期
上場を目指す場合、証券会社(J-Adviser)、監査法人、弁護士事務所、社会保険労務士、税理士などの専門家との連携が不可欠です。特に証券会社と監査法人の選定は早期に行うことをお勧めしています。
地方企業の場合の工夫
地方企業の場合、物理的な距離が課題となります。オンラインツールを活用した連携やクラウドシステムでの情報共有など、デジタル化によって効率化できる部分が増えています。FinanScope もそのようなツールの一つとして、地理的制約を克服するための機能を提供しています。
3. 財務や会計に関するよくある質問
・会計監査対応のポイントは何ですか?
上場準備における財務・会計面の整備は、成功への重要な鍵となります。特に初めて会計監査を受ける企業にとって、その準備は大きなハードルとなり得ます。
早期の準備開始
会計監査対応は上場準備の核となる部分です。監査法人の選定から始まり、予備調査(ショートレビュー)、本監査と段階的に進んでいきます。特に初めて第三者による会計監査を受ける企業にとっては、準備に時間がかかることが一般的ですので、早めに着手することをお勧めしています。
月次決算の高度化
会計監査への対応で最も重要なのは、月次決算の高度化です。単なる売上・利益の把握ではなく、貸借対照表項目も含めた適切な月次決算を行うことが、スムーズな監査対応につながります。具体的には以下のような取り組みが必要です。
- 会計方針の明確化と統一
- 勘定科目体系の整備
- 月次での棚卸資産や固定資産の管理
- 引当金の月次計上
- 証憑管理の徹底
・予実管理体制の構築方法は?
予実管理の整備は、上場審査において特に注目される部分の一つです。計画に基づいた経営ができているかどうかは、持続的成長の重要な指標と捉えられています。
予実管理の重要性
予実管理体制の整備状況は重要な審査ポイントとなります。予算から実績に至るまでのプロセスが適切に管理されていることが求められます。
段階的な体制構築
予実管理体制は一般的に以下のような段階で整備していきます。
- 単年度予算の策定プロセスの確立
- 月次での実績分析と振り返り
- 差異分析と対応策の検討
- ローリング方式の導入
- 中期経営計画との連動
・ストックオプション制度は作るべきですか?
「ストックオプション制度は作った方がいいのか」という質問も多くいただきます。経営陣と従業員のインセンティブ設計は、上場企業としての価値向上において重要なポイントです。特にストックオプション制度に関しては、その導入の是非について多くの相談が寄せられます。
経営方針との整合性
ストックオプション制度の導入については、「経営者のスタンスによって異なる」というのが私たちの基本的な考えです。株主と経営陣・従業員の利害を一致させ、長期的な企業価値向上に向けたインセンティブとなるメリットがある一方で、既存株主の株式価値の希薄化や、制度設計・運用の複雑さというデメリットもあります。
検討すべきポイント
ストックオプション制度の導入を検討する際には、以下のような点を考慮することをお勧めしています。
- 自社の企業文化や経営方針との整合性
- 対象者の範囲(経営幹部のみか、全従業員か)
- 付与条件(時間経過型か、業績達成型か)
- 発行規模と希薄化の影響
- 税務上の取り扱い
4. ガバナンスとコンプライアンスの整備
・どのような規程を整備すべきですか?
「上場までに何をすればいいのか分からない」—この声は、特に社内規程の整備において顕著です。実際に相談会でも、必要な規程の種類や優先順位について多くの質問が寄せられます。
基本的な規程整備
上場準備では多くの社内規程の整備が必要になります。最低限必要な規程としては以下のようなものが挙げられます。
- 組織規程
- 職務権限規程
- 取締役会規程
- 監査役規程
- 内部監査規程
- 経理規程
- 稟議規程
- 文書管理規程
- 情報セキュリティ管理規程
- 反社会的勢力対応規程
優先順位をつけた整備
すべての規程を一度に整備するのではなく、優先順位をつけて段階的に整備していくことが重要です。まずは組織の基本となる規程(組織規程、職務権限規程など)から着手し、徐々に範囲を拡大していくことをお勧めしています。
・内部統制はどのように構築すべきですか?
内部統制の構築は、上場準備における最も根幹的な取り組みの一つです。特に一般市場を目指す企業にとって、この部分の準備が足りないと上場審査でつまずく可能性が高くなります。
段階的なアプローチ
内部統制の構築も一度に完成形を目指すのではなく、段階的に進めていくことが重要です。特に一般市場を目指す場合、J-SOX 対応を意識した内部統制の構築が必要になります。
優先度の高いプロセス
内部統制の構築において、まず優先すべきは以下のようなプロセスです。
- 決算・財務報告プロセス
- 販売プロセス
- 購買プロセス
- 固定資産管理プロセス
- IT全般統制
各プロセスにおいて、業務記述書やフローチャートの作成、リスクと統制の特定、運用状況の評価という流れで整備を進めていきます。
5. 無料相談会のご案内
FinanScope では、上場準備に関する疑問や不安を解消するための無料オンライン相談会を実施しています。本記事でご紹介した内容以外にも、企業の状況に合わせた具体的なアドバイスを提供しています。
相談可能な内容
- IPO と M&A の比較検討
- 上場準備における必要タスクの明確化と進め方
- 企業価値評価・事業計画の策定方法
- 一般市場と TOKYO PRO Market の選択について
- FinanScope の具体的な活用方法
特徴
- 場所や時間を選ばないオンライン相談
- 上場準備の進捗状況を問わず相談可能
- 監査法人・証券会社・J-Adviser のご紹介も可能
下記ページより、相談会の予約を承っております。
https://meetings.hubspot.com/takuma6/finanscope-online
「地方から、新しい可能性を切り拓く」。その挑戦を私たち FinanScope は全力で支援します。

上場企業とそのJ-Adviser-について解説-271x153.jpg)
-247x153.png)