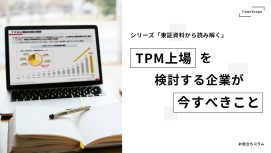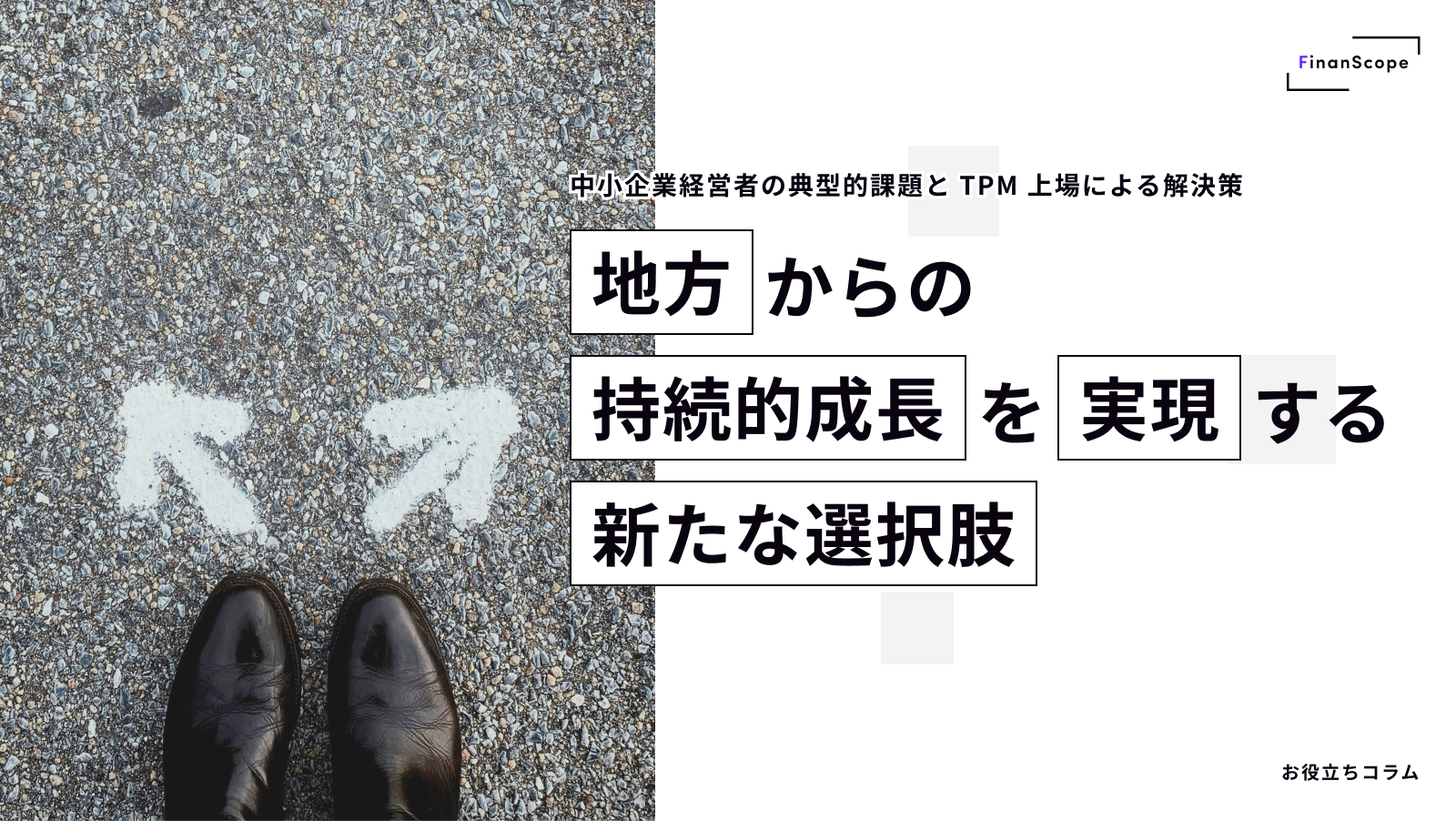
デジタルキューブ 取締役 / 公認会計士・税理士 和田 拓馬
私は香川県の出身で、都市部での勤務や香港での駐在を経て30歳で地元に戻りました。地方に戻った際、多くの優良企業の存在を再認識すると同時に、地方企業が抱える「見えない壁」も目の当たりにしました。
地方の中小企業は、長年にわたって築き上げてきた独自の強みがあります。地域との強い信頼関係、社員との密接なつながり、長期的な視点での経営判断など、都市部の企業にはない魅力を持っています。しかし、それらの強みを活かして次のステージに進むための選択肢が限られていることも事実です。
昨今、TOKYO PRO Market(TPM)への関心が高まっています。東京証券取引所の資料によれば、TPM上場企業の半数以上が東京以外に本社を置く企業です。これは、TPMが地方企業の新たな成長戦略として認識されつつあることの証左といえるでしょう。
本稿では、私自身の地方出身者としての視点と公認会計士としての経験、そしてデジタルキューブのTPM上場(2024年10月)の経験を踏まえながら、地方中小企業が直面する典型的な経営課題とTPM上場による解決策について実践的な視点からご紹介します。
目次
地方中小企業が直面する3つの「構造的課題」
地方の中小企業経営者は、景気変動や競争環境といった一般的な経営課題に加え、地方特有の「構造的課題」に直面しています。これらは単なる一時的な問題ではなく、地方という地理的・社会的環境に根ざした本質的な課題です。
1. 「経営基盤の強化」と「地域密着」のジレンマ
地方企業の多くは地域との強い結びつきを持ち、それが競争優位の源泉となっています。しかし、経営の高度化やガバナンス強化を進めようとすると、この地域密着型の経営スタイルと衝突することがあります。
例えば、関連当事者取引の整理や役員構成の見直しを行おうとすると、地域内の取引関係や人間関係に影響が及ぶことがあります。これは単なる経営上の問題ではなく、地域社会との関係性にも関わる複雑な課題です。
地方企業が上場準備を進める際には、プロフェッショナルな経営体制の構築と、創業当時からの理念や文化の継承のバランスをどう取るかという点が重要なテーマとなります。
2. 「専門人材」の確保と定着の難しさ
地方企業が直面する最も深刻な課題の一つが、専門人材の確保と定着です。特に上場準備や経営の高度化に必要な専門知識を持つ人材は地方では極めて限られています。
当社が上場準備を始めた2022年秋の時点では、上場に必要な専門知識を持つ人材は社内にほとんどいませんでした。特に地方では、以下のような人材確保の困難さがあります。
- 採用市場の狭さ:経理・財務・法務などの専門人材の絶対数が少ない
- キャリアパスの限定:専門職としてのキャリア発展の機会が限られる
- 情報格差:最新の業界動向や専門知識へのアクセスが制限される
この課題は、単に「採用を強化する」というレベルの対応では解決できない構造的な問題です。
3. 「成長資金の調達」と「地域金融との関係」のバランス
地方企業の資金調達は従来、地元金融機関との関係を基盤としてきました。上場という選択肢を検討する際、多くの企業は『なぜ融資ではなく上場という道を選ぶのか』という視点での対話が金融機関と生じることがあります。融資と資本調達はそれぞれ異なる性質を持ち、企業の成長段階や目標によって最適な選択肢が変わってきます。
また、ベンチャーキャピタルなどの成長資金提供者とのネットワークも地方では限られており、新たな事業展開や設備投資のための資金調達手段が制約されるという課題もあります。
これら「構造的課題」への従来の対応とその限界
これらの課題に対して、従来はどのような対応が取られてきたでしょうか。そしてそれにはどのような限界があったのでしょうか。
1. 段階的な組織強化アプローチ
多くの地方企業では、組織体制の強化を徐々に進めていくアプローチが取られてきました。例えば、毎年少しずつ管理部門の人員を増やす、外部研修を通じて既存社員のスキルアップを図るなどの方法です。
限界点
- 変化のスピードが遅く、事業環境の変化に追いつかない
- 組織全体の意識改革につながりにくい
- 経営者の強いコミットメントがなければ途中で頓挫しやすい
2. 外部コンサルタントの活用
専門知識やノウハウを補うために、外部のコンサルタントを活用するアプローチも一般的です。
限界点
- コスト負担が大きい(年間1,000万円程度の費用が一般的)
- 知識やノウハウが社内に蓄積されにくい
- 地方特有の事情や企業文化への理解が不十分なケースも
3. 銀行融資中心の資金調達
資金調達については、地元金融機関からの融資を中心とするアプローチが主流でした。
限界点
- 担保や保証人要件が成長の阻害要因になることも
- 融資審査の厳格化により、成長資金を調達しづらい
- 返済義務があるため、挑戦的な事業展開が制限される
これらの従来型アプローチは、一定の効果はあるものの、地方企業が抱える構造的課題を根本から解決するには限界がありました。特に、組織全体の意識改革や経営の質的転換を実現するという点では、より抜本的な変革が必要とされていたのです。
「TOKYO PRO Market 上場」という選択肢が持つ可能性
では、これらの構造的課題に対して、TOKYO PRO Market(TPM)上場はどのような解決策となり得るのでしょうか。TPM の特性を踏まえた上で、具体的な解決メカニズムを見ていきましょう。
TPM 市場の特性と地方企業との親和性
TPM は、2009年に開設された、特定投資家(プロ投資家)向けの市場です。一般市場と比較して、以下のような特徴があります。
- 形式基準の柔軟性:株主数や流通株式比率などの数値基準がない
- 審査プロセスの違い:J-Adviser(認定を受けた証券会社等)が上場審査を担当
- 準備期間の短縮:実質2年程度での上場が可能
- コスト面での優位性:一般市場と比較して上場・維持コストが低い
これらの特徴は、地方企業が抱える構造的課題と密接に関連しています。特に形式基準がないことで、地域に根差した経営スタイルを維持しながらも上場という選択肢を取ることができるという点が重要です。
地方金融機関の TPM 支援への参入
注目すべき新しい動きとして、地方金融機関が TPM 支援に乗り出し始めているという点があります。例えば、佐賀銀行が「J-アドバイザー」資格を取得するなど、地域に根差した形での上場支援体制も整いつつあります。
これは、従来の「融資中心の関係性」から「企業の成長を多面的に支援する関係性」への転換を示すものであり、地方企業にとって大きな意味を持ちます。
具体的な課題解決メカニズム:TPM 上場が変える3つの局面
TPM 上場は、先に挙げた地方中小企業の構造的課題に対して、具体的にどのように作用するのでしょうか。特に重要な3つの局面から見ていきます。
第1の局面:経営の「見える化」を通じた組織変革
TPM 上場準備のプロセスでは、経営の「見える化」が進みます。具体的には以下のような変化が生じます。
- 月次決算体制の確立:財務状況の早期把握と迅速な意思決定が可能に
- 予算管理の徹底:目標と実績の乖離を定量的に分析する文化が醸成される
- 意思決定プロセスの明確化:取締役会の役割が明確になり、重要事項の検討が充実
上場準備を通じて月次決算体制の確立や予実管理の仕組み構築が進むことで、経営の見える化が実現します。これは単なる業務改善ではなく、組織全体の意思決定の質を高める本質的な変革となります。
これらの変化は「経営基盤の強化」と「地域密着」のジレンマを解消する方向に作用します。なぜなら、透明性の高い経営プロセスは、地域からの信頼を高めることにつながるからです。
第2の局面:「専門人材の誘引力」の強化
上場企業というステータスは、人材採用において大きなアドバンテージとなります。特に地方企業にとって、以下のような効果が期待できます:
- U ターン人材の獲得:都市部で経験を積んだ地元出身者にとって魅力的な就職先に
- 成長志向の若手人材の確保:地元就職を検討する学生に対するアピールポイントに
- 専門人材の誘引:経理・財務・法務などの専門職にとってのキャリアパスとして魅力的に
上場企業としての知名度向上は、特に人材採用において大きなアドバンテージとなり得ます。これは「専門人材」の確保と定着という構造的課題を解消する重要な一歩となります。
第3の局面:「資金調達の多様化」と「地域金融との関係深化」の両立
TPM 上場により、資金調達の選択肢が広がるという直接的な効果に加え、地域金融機関との関係性も変化します:
- 資金調達手段の多様化:第三者割当増資やファイナンス・スキームの活用が可能に
- 金融機関との関係性の変化:「貸し手・借り手」から「パートナー」という関係への転換
- 信用力の向上:上場企業としての信用力向上による借入条件の改善可能性
上場により金融機関との関係性も変化し、より戦略的なパートナーシップへと発展する可能性があります。
これらの変化は「成長資金の調達」と「地域金融との関係」のバランスという課題に対する有効な解決策となります。
TPM 上場企業の実例から学ぶ成功要因
多くのTPM上場企業の事例を見ると、成功企業に共通する要因がいくつか見えてきます。ここでは、特に地方企業の成功に関わる要因を3つ紹介します。
要因1:「地域の強み」と「経営の高度化」の融合
成功している企業は、地域との結びつきや地域資源の活用という強みを維持しながらも、経営管理体制の高度化を実現しています。これは「二者択一」ではなく「両立」の発想が重要です。
具体的には…
- 地域の取引先との関係を維持しながらも、取引条件の透明性・適正性を確保
- 地域の人材を活かしつつ、必要に応じて外部から専門人材を招聘
- 地域に根差した企業理念を維持しながら、経営判断の透明性を高める
要因2:段階的な体制構築アプローチ
上場準備は、一度に完璧な体制を目指すのではなく、段階的に取り組むことが成功の鍵となります。特に地方企業の場合、リソースが限られているため、優先順位を明確にした取り組みが効果的です。
成功企業に見られる段階的アプローチの例
- 初期段階では月次決算体制の確立に注力
- 次に予実管理の仕組み構築に焦点
- さらに内部統制や情報開示体制の整備へと展開
要因3:デジタル技術の効果的活用
地理的な制約を克服するために、デジタル技術を効果的に活用している企業が成功しています。特に上場準備プロセスにおいては、以下のような活用例が見られます。
- クラウドベースの会計システムの導入による決算の効率化
- Web 会議システムを活用した証券会社・監査法人とのコミュニケーション
- プロジェクト管理ツールによる上場準備タスクの可視化と進捗管理
当社が2022年に上場準備を始めた際にも、テクノロジーの活用は課題の一つでした。タスク管理はメールと Excel で行われ、バージョン管理の混乱や情報共有の非効率さを実感しました。
この経験から生まれたのが、上場準備クラウド「FinanScope」です。これは単なるツールではなく、地方企業特有の課題を解決するためのプラットフォームとして開発されました。
実務的な視点:TPM 上場準備の「始め方」
では、具体的に TPM 上場準備をどのように始めればよいのでしょうか。特に地方企業における実務的なアプローチを紹介します。
ステップ1:自社の現状把握と課題整理
まずは自社の現状を客観的に把握することから始めましょう。特に以下の点について整理することが重要です。
- 経営管理体制の現状:月次決算の状況、予実管理の仕組み、取締役会の運営状況など
- 人材・組織の現状:経理・財務・法務などの専門部署の状況、社内の専門知識レベルなど
- 資本政策の状況:株主構成、過去の資金調達履歴、今後の資金需要予測など
自社診断の結果、足りない部分が明確になれば、効率的な準備計画を立てることができます。
ステップ2:地域のネットワークを活用した専門家チームの構築
上場準備には様々な専門家のサポートが必要です。地方企業の場合、以下のようなアプローチが効果的です。
- 地方金融機関の紹介ネットワークの活用:最近では地方銀行が J-Adviser との連携を強化する動きも
- 地元の士業専門家との連携:公認会計士、税理士、弁護士など
- 同地域の上場企業経営者からのアドバイス:実際の経験に基づくノウハウの獲得
ステップ3:デジタル技術を活用した効率的な準備体制の構築
地理的な制約を克服するために、デジタル技術の積極的な活用が鍵となります。
- クラウド会計システムの導入:月次決算の早期化と精度向上
- 上場準備専用のプロジェクト管理ツール:タスクの可視化と進捗管理
- Web 会議システムの活用:物理的な移動を最小限に抑えた専門家との連携
これらのデジタル技術の活用により、地方企業特有の「物理的距離」という制約を克服し、効率的な上場準備が可能になります。
地方企業経営者へのメッセージ ― 新しい成長の選択肢として
最後に、地方企業の経営者の皆様へのメッセージとして、TPM 上場を検討する際の視点を共有したいと思います。
「上場」を目的化せず、「持続的成長のための手段」として捉える
上場自体を目的化するのではなく、自社の持続的成長のための手段として捉えることが重要です。これは、「なぜ上場するのか」という本質的な問いに立ち返ることでもあります。
私たちデジタルキューブが TPM 上場を目指した最も根本的な理由は、「会社を永続させたい」という思いでした。創業者である小賀の言葉を借りれば、「私が死んでも会社が存続できる環境を作りたい」という思いでした。この言葉には、単に会社を存続させるという経営者としての責任だけでなく、地域社会への貢献や従業員とその家族の生活を支え続けるという使命感が込められていると考えています。
上場という選択肢は、このような企業の永続性を実現するための一つの手段として位置づけられるべきでしょう。特に TPM 上場は、形式基準にとらわれずに自社のペースで段階的に成長できるという特性から、地方企業にとって現実的な選択肢となり得ます。
「地域との結びつき」を強みとして活かす成長モデルの構築
地方企業の多くは、地域との強い結びつきを持っています。これは決して捨て去るべき「古い体質」ではなく、むしろ差別化の源泉となる「強み」です。TPM 上場を通じた経営の高度化は、この強みを損なうものではなく、むしろ強化するものであるべきです。
実際に、上場を果たした地方企業の多くは、以下のようなアプローチで地域との関係性を維持・強化しています。
- 地域の取引先との関係を「個人的なつながり」から「組織的な協力関係」へと発展
- 地域の金融機関と「融資」という枠を超えた「成長パートナー」としての関係構築
- 地域の教育機関との連携強化による人材育成・採用の仕組み化
これらは、TPM 上場という新たな選択肢を取りながらも、地域企業としてのアイデンティティを維持し、むしろそれを強化する方向性を示すものです。
次世代に向けた「事業承継」の新たな形の実現
多くの地方企業にとって、事業承継は喫緊の課題です。特に創業者一族による事業承継が難しい場合、「誰に引き継ぐのか」という問題に直面します。
TPM 上場は、この課題に対する新たな解決策となり得ます。なぜなら、上場により経営と所有が分離され、企業としての永続性を確保しやすくなるからです。お客様に価値を提供し続け、従業員とその家族の生活を支え、地域社会に貢献する―そういった価値のある会社は、創業者がいなくなっても存続していくべきなのです。
TPM 上場は、こうした「事業の永続性」を実現するための現実的な選択肢の一つとなるでしょう。
まとめ:地方から、新しい可能性を切り拓く
本稿では、地方中小企業が直面する構造的課題と TPM 上場による解決策について解説してきました。ここで改めて重要なポイントを整理しておきます。
- 地方中小企業は独自の「構造的課題」に直面している
- 「経営基盤の強化」と「地域密着」のジレンマ
- 「専門人材」の確保と定着の難しさ
- 「成長資金の調達」と「地域金融との関係」のバランス
- TPM 上場はこれらの課題を解決する有効な選択肢となり得る
- 経営の「見える化」を通じた組織変革
- 「専門人材の誘引力」の強化
- 「資金調達の多様化」と「地域金融との関係深化」の両立
- TPM 上場を成功させるには、地方企業ならではのアプローチが重要
- 「地域の強み」と「経営の高度化」の融合
- 段階的な体制構築アプローチ
- デジタル技術の効果的活用
私たちは「地方から、新しい可能性を切り拓く」という理念のもと、上場準備クラウド「FinanScope」の開発・運営を通じて、地方企業の上場支援に取り組んでいます。TPM 上場という選択肢が、地方企業の持続的な成長と地域経済の活性化につながることを願ってやみません。
「一つの会社の成長は、地域全体の可能性を広げる」、この信念のもと、私たちは地方企業の挑戦を今後も支援していきます。
無料相談会のご案内
FinanScope では、上場準備に関する疑問や不安を解消するための無料オンライン相談会を実施しています。本記事でご紹介した内容以外にも、企業の状況に合わせた具体的なアドバイスを提供しています。
相談可能な内容
- IPO と M&A の比較検討
- 上場準備における必要タスクの明確化と進め方
- 企業価値評価・事業計画の策定方法
- 一般市場と TOKYO PRO Market の選択について
- FinanScope の具体的な活用方法
特徴
- 場所や時間を選ばないオンライン相談
- 上場準備の進捗状況を問わず相談可能
- 監査法人・証券会社・J-Adviser のご紹介も可能
下記ページより、相談会の予約を承っております。
URL:https://meetings.hubspot.com/takuma6/finanscope-online
一社一社の状況は異なりますが、「地方から、新しい可能性を切り拓く」。その挑戦を私たち FinanScope は全力で支援します。

上場企業とそのJ-Adviser-について解説-271x153.jpg)
-247x153.png)