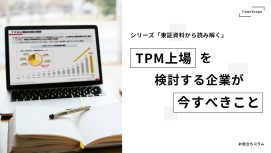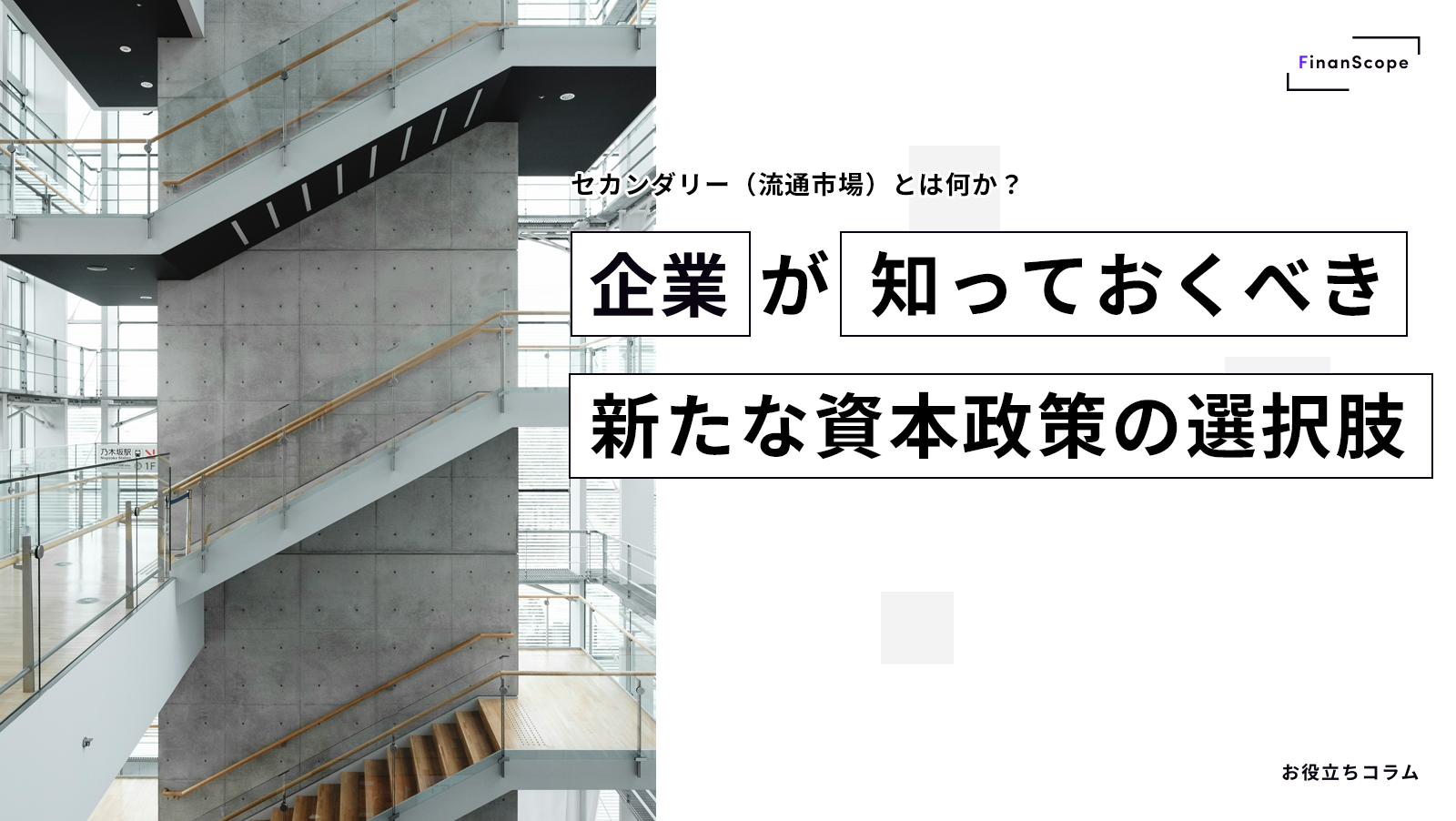
デジタルキューブ 取締役 / 公認会計士・税理士 和田 拓馬
企業の成長戦略として、これまで IPO を含めたスタートアップの資金調達が注目されておりましたが、近年「セカンダリー(流通市場)」にも光が当たり始めています。このセカンダリーは従来の資金調達の枠を超えた、多様なメリットを提供する可能性を秘めています。
本稿では、セカンダリーの基本概念から、企業が検討すべき具体的なケース、そして最新の市場動向まで、実務的な観点から解説していきます。
目次
はじめに – セカンダリーが注目される背景
私たちデジタルキューブが2024年に TPM 上場を実現する過程で、様々な企業の成長戦略について考える機会がありました。その中で感じたのは、「IPO ありき」の発想から脱却し、企業の実情に応じた最適な成長戦略を選択することの重要性です。
例えば、地方企業の多くは、堅実な経営基盤と地域に根ざした事業モデルを持っています。こうした企業にとって、大規模な資金調達を前提とした IPO が必ずしも最適解とは限りません。むしろ、セカンダリーという選択肢によって、着実な企業価値の向上と既存株主の利益確保を両立できる可能性があるかもしれません。
なぜ今、セカンダリーが注目されているのでしょうか。それは、企業の成長段階や事業特性に応じた、より柔軟な資本政策のニーズが高まっているからです。特に、優秀な人材確保が課題となっている地方企業にとって、ストックオプションなどの株式報酬制度と組み合わせたセカンダリーの活用は、新たな競争力の源泉となり得ます。
セカンダリー(流通)市場の基本概念
セカンダリーを理解するために、まずはプライマリーとの違いを明確にしましょう。
プライマリー(発行)市場とセカンダリー(流通)市場の違い
プライマリー市場とは、企業が新株を発行して投資家から直接資金を調達する市場です。未上場時のシーリーズA・Bなどの資金調達や IPO がこれに該当し、企業は調達した資金を事業拡大や設備投資に活用できます。
一方、セカンダリー市場は、既に発行された株式を投資家同士が売買する市場です。この場合、企業は直接的な資金調達を行いませんが、株式の流動性が生まれ、既存株主が保有株式を現金化することが可能になります。
※上場株式の売買についても流通市場という意味ではセカンダリー市場になりますが、ここでは主に IPO 前の未上場株式の売買を前提として説明します。
セカンダリーの具体的な仕組みと特徴
セカンダリー上場では、企業は新株を発行せず、創業者や既存投資家が保有する株式の一部を市場で売却します。この仕組みにより、従来のプライマリー上場とは異なる特徴的なメリット・デメリットが生まれます。
企業側から見ると、最大のメリットは希薄化を伴わずに既存株主に売却機会を提供できることです。新株発行による株式の希薄化は、既存株主の持分比率を下げる要因となりますが、セカンダリーではこの問題を回避できます。また、株主構成の変化によっては、より適切なガバナンス体制を期待することもできます。機関投資家などの専門的な投資家が株主に加わることで、経営に対する建設的な助言や監督機能の向上が見込めるケースもあります。
一方で、企業側のデメリットとして、直接的な資金調達ではないため企業にお金が入らないという点があります。事業拡大のための資金が必要な企業にとって、これは大きな制約となる可能性があります。さらに、株主構成の変化により経営への影響を受ける可能性もあります。新たに株主となる投資家の投資方針や経営に対する考え方によっては、従来の経営方針の変更を求められるケースも考えられます。
株主側のメリットは明確で、保有株式の現金化機会の確保が最も重要な点です。これまで非流動資産として保有していた株式を、市場で売却することにより現金化できるようになります。株式の流動性向上により、必要に応じて段階的な売却による資金回収が可能となることも大きな魅力です。創業者であれば事業承継資金として、投資家であれば他の投資機会への資金として活用できます。
しかし、株主側にもデメリットは存在します。株式の希薄化は避けられるものの、売却により自身の持分は確実に減少します。将来的な企業価値向上の恩恵を受ける機会が限定的になるという側面があります。また、市場環境により売却価格が変動するリスクも無視できません。上場時の市場状況や投資家の需要により、期待していた価格で売却できない可能性もあります。
| プライマリー市場(発行市場) | セカンダリー市場(流通市場) | |
|---|---|---|
| 定義 | 企業が新株を発行して投資家から資金を調達する市場 | 既存の株式を投資家間で売買する市場(IPO前含む) |
| 該当例 | シリーズA・Bなどの資金調達、IPO | 未上場株式の売却、上場株の売買(今回は未上場を主対象) |
| 株式の発行有無 | 新たに発行される(希薄化あり) | 発行されない(既存株主の株式を売却) |
| 資金の流れ | 企業に直接入る | 企業には入らず、売却株主に渡る |
| 企業側のメリット | 事業拡大・設備投資資金の確保 | 希薄化せずに売却機会を提供可能 ガバナンス強化の契機に |
| 企業側のデメリット | 株式の希薄化、調達コストや開示負担 | 資金は入らない 株主構成変化による影響 |
| 株主側のメリット | IPOによる価値向上の期待 | 現金化機会の確保 段階的な資金回収が可能 |
| 株主側のデメリット | 株式のロックアップや上場失敗リスク | 持分の減少 価格変動リスク |
| 日本の現状 | 成熟しており制度も整備済 | 事例は限定的だが、注目度上昇中(特にプロマーケット) |
日本における現状と課題
日本では、未上場株式のセカンダリー取引の事例はまだ限定的です。しかし、スタートアップエコシステムの発展や、多様な成長戦略へのニーズの高まりを受けて、徐々に注目が集まっています。我々が近年注目している、プロマーケット市場においても、セカンダリー活用の実現可能性が高まっていると感じています。
セカンダリー市場の新たな展開 – Nstock の挑戦
セカンダリー市場を語る上で見逃せないのが、日本のスタートアップエコシステムに新たな風を吹き込もうとしている Nstock 株式会社の取り組みです。
従来のセカンダリーの課題
これまでのセカンダリー市場には、大きな制約がありました。最も重要な課題は、IPO 後でなければ株式の流動性が確保できないことです。特にスタートアップで働く従業員にとって、ストックオプションや株式報酬を受け取っても、実際に現金化できるのは企業が IPO してからという状況でした。
この状況は、優秀な人材の確保において大きなハンディキャップとなっていました。特に地方企業の場合、都市部の企業や外資系企業との人材獲得競争において、株式報酬の魅力を十分に訴求できないという課題がありました。
Nstock が目指す「社内取引所」の仕組み
Nstock は、SmartHR を創業した宮田昇始氏が新たに立ち上げた会社で、「スタートアップエコシステムをブーストし、日本から Google 級の会社を生み出す」ことをミッションに掲げています。同社が提供する株式報酬管理 SaaS は、企業が従業員に付与するストックオプションの設計、株価算定、運用効率化などをサポートしています。
注目すべきは、Nstock がセカンダリー事業への挑戦を表明していることです。同社は、株式報酬 SaaS で培った知見と技術を活かし、未上場企業の株式やストックオプションが IPO 前でも売買できるような仕組みを構築することを目指しています。
この仕組みは「社内取引所」のような形で設計され、企業側が参加者や取引条件をコントロールできる点が特徴です。これにより、企業は株主構成の管理を維持しながら、従業員や投資家に流動性を提供することが可能になります。
日本のスタートアップエコシステムへの影響
Nstock のような取り組みが実現すれば、日本のスタートアップエコシステム全体に大きな影響をもたらす可能性があります。スタートアップで働く人々がより安心して株式報酬を受け取れるようになり、優秀な人材の流動性が高まることが期待されます。
これは地方企業にとっても大きなチャンスです。都市部との人材獲得競争において、株式報酬の魅力を十分に訴求できるようになれば、地方企業の競争力は大幅に向上するでしょう。
セカンダリーが企業にもたらすメリット
セカンダリーは、従来の資金調達の枠を超えた多様なメリットを企業に提供します。
既存株主の流動性確保
創業者や初期投資家にとって、セカンダリーは重要な EXIT の機会を提供します。これまで多くの地方企業では、事業承継や資金回収の手段が限られていました。セカンダリーにより、段階的な株式売却を通じて資金を回収しながら、企業経営に継続的に関与することが可能になります。
従業員の持株及びストックオプションについても同様です。長年にわたって企業の成長に貢献してきた従業員が、その対価として受け取った株式を適切なタイミングで現金化できることは、モチベーション向上と人材定着に大きく貢献します。
段階的な資本政策の実現
セカンダリーは、企業の成長段階に応じた柔軟な資本政策を可能にします。これまでは、一度調達を行った株主と経営方針が一致しない場合でも、セカンダリー市場がないために売却の機会を提供できず、経営方針の違いを抱えたまま成長を目指して行くようなこともありました。セカンダリー市場があることで、企業側と方針が合わない投資家にはExitの機会を提供し、新たな投資が関与することで、株主構成を入れ替えながら、一丸となって経営を推し進めることができるようになります。
人材確保における競争力向上
特に地方企業にとって重要なのが、人材確保における競争力向上です。ストックオプション制度と組み合わせることで、単なる給与以外のインセンティブを提供できるようになります。
Nstock のような IPO 前の段階での株式流動性を確保する仕組みが普及すれば、地方企業でも都市部の企業と同等の魅力的な株式報酬制度を提供できるようになります。これは、優秀な人材のUターンやIターンを促進する重要な要因となり得ます。
企業がセカンダリーを検討すべきケース
どのような企業がセカンダリーを検討すべきでしょうか。以下のような特徴を持つ企業に特に適していると考えられます。
どのような企業に適しているか
セカンダリー市場が適している企業は、ベンチャーキャピタルからの投資期間が満期に近づき、エグジット戦略の選択肢が必要な企業や、今後の経営において IPO と M&A のいずれかの選択で検討を要する企業、事業の多角化または集中化といった経営戦略において株主と経営陣の間で見解の相違が生じている企業などが考えられます。
事業承継を検討している企業にとっても、セカンダリーは非常に有効な選択肢となります。創業者が段階的に経営から身を引きながら、これまでの投資を適切に回収できる仕組みを提供できます。後継者が事業基盤を引き継ぎながら、IPO を目指していくという選択肢も大変面白い取り組みです。
優秀な人材確保が課題の企業では、セカンダリーと株式報酬制度を組み合わせることで、新たな採用戦略を展開できます。特に、専門性の高い人材や経営幹部候補の確保において、大きなアドバンテージとなるでしょう。
TPM との親和性
TOKYO PRO Market(TPM)は、地方企業の上場も多く、創業者一族の他にも役員、従業員が株式やストックオプションを保有している場合があります。一般市場への IPO を目指している場合もそうでない場合も、TPM 上場後から IPO までの段階で売却できる機会を提供することは、企業側にとっても株主にとってもこれまでにない選択肢を提供できるものとなります。また、TPM の流動性を高めることにも効果を発揮することになり、この流動性の担保に向けて、私たちも継続的に関与していきたいと思います。
地方企業特有の活用シーン
U ターン人材の獲得戦略において、セカンダリーは強力な武器となります。都市部で経験を積んだ優秀な人材が地元に戻る際、給与面での条件だけでは都市部企業との競争は困難です。しかし、株式報酬によって、IPO またはセカンダリーによるキャピタルゲインの可能性を提示できれば、魅力的なオファーとなるでしょう。
地域密着型ビジネスでの差別化においても、セカンダリーは有効です。地域の顧客や取引先から見て、「地元の上場企業」という地位は大きな信頼感を生み出します。これは、全国展開を目指す企業だけでなく、地域に根ざした事業を継続する企業にとっても重要な価値となります。
今後の展望と課題
セカンダリー市場を取り巻く環境は、急速に変化しています。
市場環境の変化
投資家ニーズの多様化は、セカンダリー市場にとって追い風となっています。機関投資家の中には、急成長よりも安定した収益性を重視する投資方針を持つファンドが増えており、セカンダリー案件への関心も高まっています。
規制環境の整備状況も、今後の動向を左右する重要な要因です。現在、様々な機関や企業、団体において、多様な資金調達手段の提供と投資家保護のバランスを取るための制度整備が進められています。これらの動向は、セカンダリー市場の発展に大きな影響を与えるでしょう。
テクノロジーによる市場インフラの進化も見逃せません。Nstock のような新たなサービスだけでなく、ブロックチェーン技術やデジタル証券の普及により、従来の株式取引の枠組みを超えた新たな流動性確保の仕組みが登場する可能性があります。
地方経済への影響
セカンダリー市場の発展は、地方経済に多大な影響をもたらす可能性があります。
新たな成長モデルの可能性として、地方企業が従来の「資金調達→事業拡大→ IPO →さらなる事業拡大」というパターンから脱却し、「着実な収益確保→ TPM 上場→事業拡大→セカンダリー→ IPO →さらなる収益向上」という循環を構築できるかもしれません。
エコシステム形成への期待も大きくなっています。セカンダリーを通じて成功する地方企業が増えれば、その企業の従業員や関係者が新たな起業にチャレンジするケースも増えるでしょう。これにより、地方におけるスタートアップエコシステムの形成が促進される可能性があります。
人材流動性の向上は、地方企業にとって特に重要な変化となるでしょう。優秀な人材が、都市部の大企業だけでなく、地方の成長企業という選択肢を真剣に検討するようになれば、地方経済の活性化に大きく貢献します。
Nstock のような新サービスがもたらす変化
Nstock のような革新的なサービスが普及すれば、日本のスタートアップエコシステム全体の活性化が期待できます。特に、株式報酬の魅力度向上により、優秀な人材がスタートアップや成長企業への転職をより積極的に検討するようになるでしょう。
地方企業の人材確保戦略への影響も見逃せません。未上場段階での株式流動性が確保されれば、地方企業でも都市部企業と同等の魅力的な株式報酬制度を提供できるようになります。これは、地方創生の観点からも非常に重要な変化となるでしょう。
まとめ – 多様な成長戦略の一つとして
セカンダリー(流通市場)は、従来の IPO 一辺倒の企業成長戦略に、新たな選択肢を提供します。
Nstock のような革新的なサービスの登場により、従来の制約を超えた新たな可能性が開かれつつあります。テクノロジーの力を借りることで、地方企業でも都市部企業と同等の競争力を持つ人材確保戦略を展開できる時代が到来するかもしれません。
私たちが自身の上場準備を通じて学んだのは、企業の持続的成長において最も重要なのは、自社の特性と市場環境を正しく理解し、それに基づいた最適な戦略を選択することです。セカンダリーという新たな選択肢を含めて、多角的に検討することで、より良い成長戦略を描けるはずです。
地方企業の皆様におかれましては、ぜひセカンダリーという選択肢について検討してみてください。それが、企業の新たな成長と地方経済の活性化につながることを期待しています。
無料相談会のご案内
上場準備に関する疑問や不安は、企業によって様々です。セカンダリーに関する基本的な疑問から、「自社にとって最適な上場戦略は何か?」という根本的な問いまで、私たちは多くの経営者の方々と対話を重ねてきました。
そこで、まずは「無料個別相談会」で、皆様の課題やニーズをお聞かせください。企業独自の状況を踏まえた上で、具体的な道筋をご提案させていただきます。
相談可能な内容
- 企業価値評価・事業計画の策定方法
- 一般市場と TOKYO PRO Market の選択について
- TOKYO PRO Market 上場前後での Exit について
- 上場準備における必要タスクの明確化と進め方
特徴
- 場所や時間を選ばないオンライン相談
- 上場準備の進捗状況を問わず相談可能
- 監査法人・証券会社・J-Adviser のご紹介も可能
下記ページより、相談会の予約を承っております。
URL:https://meetings.hubspot.com/takuma6/finanscope-online
「地方から、新しい可能性を切り拓く」。一社一社の状況は異なりますが、その挑戦を私たち FinanScope は全力で支援します。

上場企業とそのJ-Adviser-について解説-271x153.jpg)
-247x153.png)