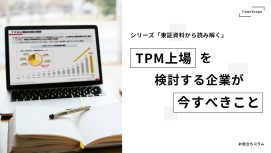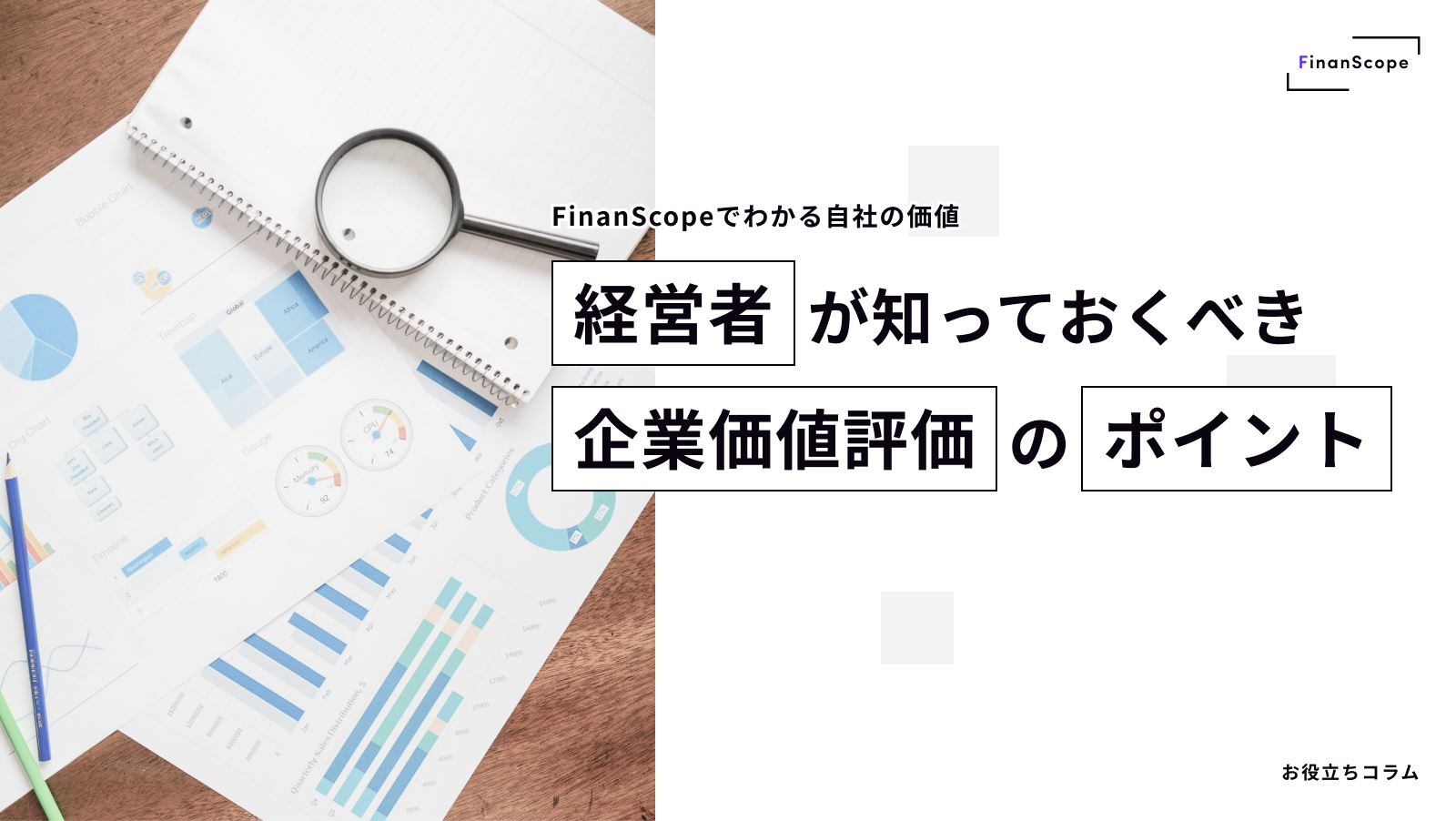
デジタルキューブ 取締役 / 公認会計士・税理士 和田 拓馬
企業価値評価 —— この言葉に対して、「専門家に任せるもの」「上場や M&A の時だけ必要なもの」という印象をお持ちの経営者の方も多いのではないでしょうか。しかし実際には、企業価値評価は経営判断の重要な基盤となり、成長戦略を考える上での羅針盤ともなる重要なツールです。本稿では、私自身の M&A 経験や上場準備で直面した課題を踏まえながら、経営者が知っておくべき企業価値評価のポイントを解説します。
目次
なぜ今、企業価値評価が重要なのか
「自社(他社)の企業価値はいくらなのか」— この問いに回答できる経営者はどれほどいるでしょうか。
当社は2022年に株式会社ヘプタゴンとの M&A を経験しましたが、そこで最も慎重かつ丁寧に対応したのが企業価値評価でした。M&A の交渉において、「なぜその金額なのか」を説明するためのロジックが必要でしたが、非上場企業の場合、市場で観測できる株価がないため、様々な手法を用いて価値を算定する必要がありました。
この経験を通じて気づいたのは、企業価値評価は論理的根拠のみから計算されるものではなく、自社(他社)の将来性や強み、独自性、将来の戦略、ひいては経営者の「想い」を「価値」として可視化するプロセスであり、ある種の「アート」であるということです。自社(他社)を客観的に見つめ直す絶好の機会でもあります。
企業価値評価が特に重要となるのは、主に以下のような場面です。
- 上場準備時:IPO における想定株価の算定基礎
- M&A交渉時:売買価格の根拠
- 資金調達時:投資家への説明材料
- 事業承継時:適正な株式評価
- 経営判断時:事業戦略の評価や資源配分の判断材料
特に近年では、TOKYO PRO Market(TPM)への上場を目指す地方企業が増加しており、より早い段階から企業価値評価に取り組む企業が増えています。2023年には32社、2024年には50社が TPM に新規上場を果たし、累計で約170社にまで成長してきました。このような流れの中で、企業価値評価の重要性はますます高まっているのです。
3つの代表的な評価手法と特徴
企業価値評価に絶対的な正解はありません。むしろ、複数の評価手法を併用し、それぞれの視点から自社の価値を多角的に検討することが重要です。代表的な3つの評価手法を見ていきましょう。
1. DCF法(Discounted Cash Flow法)
DCF法は、企業が将来生み出すキャッシュフローを現在価値に割り引いて企業価値を算定する方法です。
特徴
- 企業の将来性や成長性を直接的に評価に反映できる
- 事業計画に基づく評価のため、経営者の意図を反映しやすい
- 割引率や永久成長率などの前提条件により結果が大きく変動する
実務上のポイント
私たちの経験では、予測期間(通常3〜5年間)の設定と、その先の継続価値(ターミナルバリュー)の算定が特に重要です。あまりに楽観的な事業計画は説得力を欠くため、過去の実績との整合性や業界動向との比較が必須となります。
特に地方企業では、地域の特性や独自の強みが将来のキャッシュフローに与える影響を適切に見積もる必要があります。例えば、地域との強い信頼関係や取引先との安定的な関係は、将来の安定したキャッシュフローとして評価できるケースがあります。
2. 類似会社比較法
上場している類似企業の株価指標(PER、EBITDAマルチプルなど)を参考に、評価対象企業の価値を推定する方法です。
特徴
- 市場での現実の評価を反映している
- 比較的シンプルで理解しやすい
- 適切な類似企業を選定できるかが結果を左右する
実務上のポイント
類似企業の選定は、業種や規模だけでなく、事業モデルや成長フェーズ、収益構造などの類似性も考慮する必要があります。また、上場企業と非上場企業の違いを調整するため、非上場企業ではディスカウント(約20〜30%程度)を適用することも一般的です。
地方企業の場合、完全に類似する上場企業が見つからないケースも多く、その場合は複数の企業から部分的に類似する要素を抽出して比較することもあります。
3. 時価純資産法
企業が保有する資産を時価評価し、負債を差し引いて純資産価値を算定する方法です。
特徴
- 理解しやすく、客観性が高い
- 資産を多く保有する企業に適している
- 将来の成長性や無形資産の価値が反映されにくい
実務上のポイント
簿価と時価の差異が大きい不動産や有価証券などの資産については、適切な時価評価が必要です。特に、地方企業では長期保有の不動産など、簿価と実勢価格に大きな差がある場合も少なくありません。また、非事業資産(事業に直接使われていない資産)の扱いも重要なポイントとなります。
非上場企業・地方企業が直面する評価の課題
企業価値評価においては、非上場企業、特に地方企業は独特の課題に直面します。
情報の非対称性
市場で株価が観測できないため、客観的な評価の基準点がありません。また、経営情報の開示レベルも上場企業と比較して限定的であることが多く、外部からの評価が難しいケースがあります。
類似企業の特定の難しさ
特に地方の特性を活かした独自のビジネスモデルを持つ企業の場合、適切な比較対象となる上場企業を見つけることが困難な場合があります。
専門家へのアクセス制約
地方企業にとって、企業価値評価の専門家へのアクセスが限られていることも大きな課題です。都市部に集中する専門家との物理的な距離は、スムーズなコミュニケーションや迅速な評価更新の障壁となります。
この課題を、私自身も強く実感しました。地元である香川県にUターンした際、地方には優良企業が多く存在するものの、上場という選択肢を十分に検討できていない状況がありました。その背景には、専門的知識へのアクセスや、評価ツールの不足があったのです。
評価結果の解釈と活用の難しさ
評価結果を得ても、それをどう解釈し、経営判断に活かすかという点で苦労する企業も少なくありません。例えば、評価手法ごとに結果が大きく異なった場合の解釈や、評価結果と自社の実感とのギャップをどう埋めるかといった課題があります。
FinanScope が実現する「使える」企業価値評価
これらの課題に対して、上場準備クラウド「FinanScope」の Valuation(企業価値評価機能)は、新しいアプローチを提供します。
リアルタイム評価の実現
FinanScope Valuation の最大の特徴は、事業計画と決算書をアップロードし、類似企業を選択するだけで、DCF 法、類似会社比較法、時価純資産法の3つの方法による算定結果が即座に表示される点です。さらに、クラウド上での事業計画の修正が、リアルタイムで企業価値評価に反映される仕組みを実現しています。
例えば、「売上高が10%増加した場合」「営業利益率が2ポイント改善した場合」といったシミュレーションを即座に行い、その影響を確認できます。これにより、経営判断のスピードが大きく向上します。

地理的制約の克服
クラウドベースのサービスとして提供されるため、地理的な制約を越えて専門的な評価を行うことが可能です。都市部の専門家と同等の企業価値評価ツールに、地方からでもアクセスできます。
【活用事例】資金調達交渉での活用
実際の活用事例として、あるスタートアップ企業では資金調達の交渉において、FinanScopeを用いた企業価値評価結果を活用し、投資家への説明資料として使用しました。
「資金調達の交渉において、企業価値の主張に対する客観的なエビデンスを提示できるようになりました。事業会社との交渉では、このツールを使って算出した数字が、議論のスタートポイントとして非常に有効でした。」(株式会社Soilook 代表取締役 西藤翼 様)
※株式会社Soilook様の活用事例記事はこちら
「企業価値の評価に客観性をもたらし、チーム全体の意識を変えてくれました」
評価結果を活かした企業価値向上戦略
企業価値評価の最終的な目的は、評価を通じて自社の強みと弱みを理解し、企業価値を高めるための戦略立案にあります。評価結果を活かした企業価値向上のポイントをいくつか紹介します。
1. 事業計画における重要指標(KPI)の設定
企業価値評価のプロセスで明らかになる重要な指標(営業利益率、運転資本回転率など)を特定し、それらを改善するための具体的な施策を事業計画に組み込みます。
例えば、DCF 法の感度分析により、営業利益率の改善が企業価値に大きく影響することが分かれば、それを中長期的な KPI として設定し、定期的に進捗をモニタリングする体制を整えます。
2. 事業ポートフォリオの最適化
企業価値評価を事業部門別に行うことで、より価値創造に貢献している事業とそうでない事業を識別できます。限られた経営資源を価値創造の高い分野に集中させることで、全体の企業価値を高める戦略につながります。
実際に、ある製造業では事業別の評価を行った結果、新興国向けの事業が想定以上に高い評価となり、その後の投資戦略の優先順位付けに活用されました。
3. 適切な資本政策
企業価値評価は資本政策にも重要な示唆を与えます。例えば、負債と自己資本のバランス(資本構成)の最適化や、配当政策の検討などに活用できます。
特に TPM 上場を目指す企業では、上場前の資本政策(第三者割当増資や株式分割など)の検討において、企業価値評価が重要な基準となります。
4. コーポレートガバナンスの強化
企業価値評価において重要な要素である「将来の持続的な成長」を実現するためには、コーポレートガバナンスの強化も欠かせません。特に上場を視野に入れる企業にとって、早い段階からガバナンス体制の整備を進めることは、将来の企業価値向上につながります。
まとめ:企業価値評価を経営の羅針盤に
企業価値評価は、特別なイベント(上場や M&A)のためだけのものではありません。定期的に自社の価値を評価し、強みと課題を認識することで、より戦略的な経営判断が可能になります。
私自身、デジタルキューブでの上場準備とヘプタゴンとのM&A経験を通じて、企業価値評価の重要性を肌で感じました。それは単なる数値計算ではなく、「会社として何を大切にしているのか」「どのような強みがあるのか」を改めて言語化するプロセスでもあります。同時に、特に地方企業にとっては、専門的知識へのアクセスや評価ツールの不足という課題も明らかになりました。
FinanScope は、こうした地方企業特有の課題を解決するために生まれました。テクノロジーの力で地理的な制約を超え、すべての企業が公平に企業価値評価にアクセスできる環境を整えることで、地方からの新たな成長企業の誕生を支援したいと考えています。
2025年には FinanScope 利用企業の初めての上場が予定されており、このサービスの実効性が示される重要な転換点を迎えようとしています。この成功事例を皮切りに、より多くの地方企業が自社の価値を正しく認識し、持続的な成長への道筋を描けるようになることを願っています。
企業価値評価を通じて自社の強みを再認識し、未来に向けた展望を描く——その第一歩として、ぜひ FinanScope をご活用いただければ幸いです。
まずは無料相談会で可能性を探ってみませんか?
上場準備に関する疑問や不安は、企業によって様々です。「具体的な準備期間は?」「必要な人員体制は?」「予算規模は?」など、実務的な質問から、「本当に実現可能なのか?」という根本的な問いまで、私たちは多くの経営者の方々と対話を重ねてきました。
そこで、まずは「無料個別相談会」で、皆様の課題やニーズをお聞かせください。企業独自の状況を踏まえた上で、具体的な道筋をご提案させていただきます。
相談可能な内容
- IPO と M&A の比較検討
- 上場準備における必要タスクの明確化と進め方
- 企業価値評価・事業計画の策定方法
- 一般市場と TOKYO PRO Market の選択について
- FinanScope の具体的な活用方法
特徴
- 場所や時間を選ばないオンライン相談
- 上場準備の進捗状況を問わず相談可能
- 監査法人・証券会社・J-Adviser のご紹介も可能
下記ページより、相談会の予約を承っております。
URL: https://meetings.hubspot.com/takuma6/finanscope-online
一社一社の状況は異なりますが、「地方から、新しい可能性を切り拓く」。その挑戦を私たちFinanScope は全力で支援します。

上場企業とそのJ-Adviser-について解説-271x153.jpg)
-247x153.png)