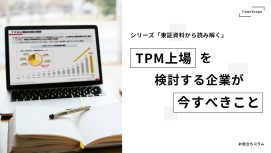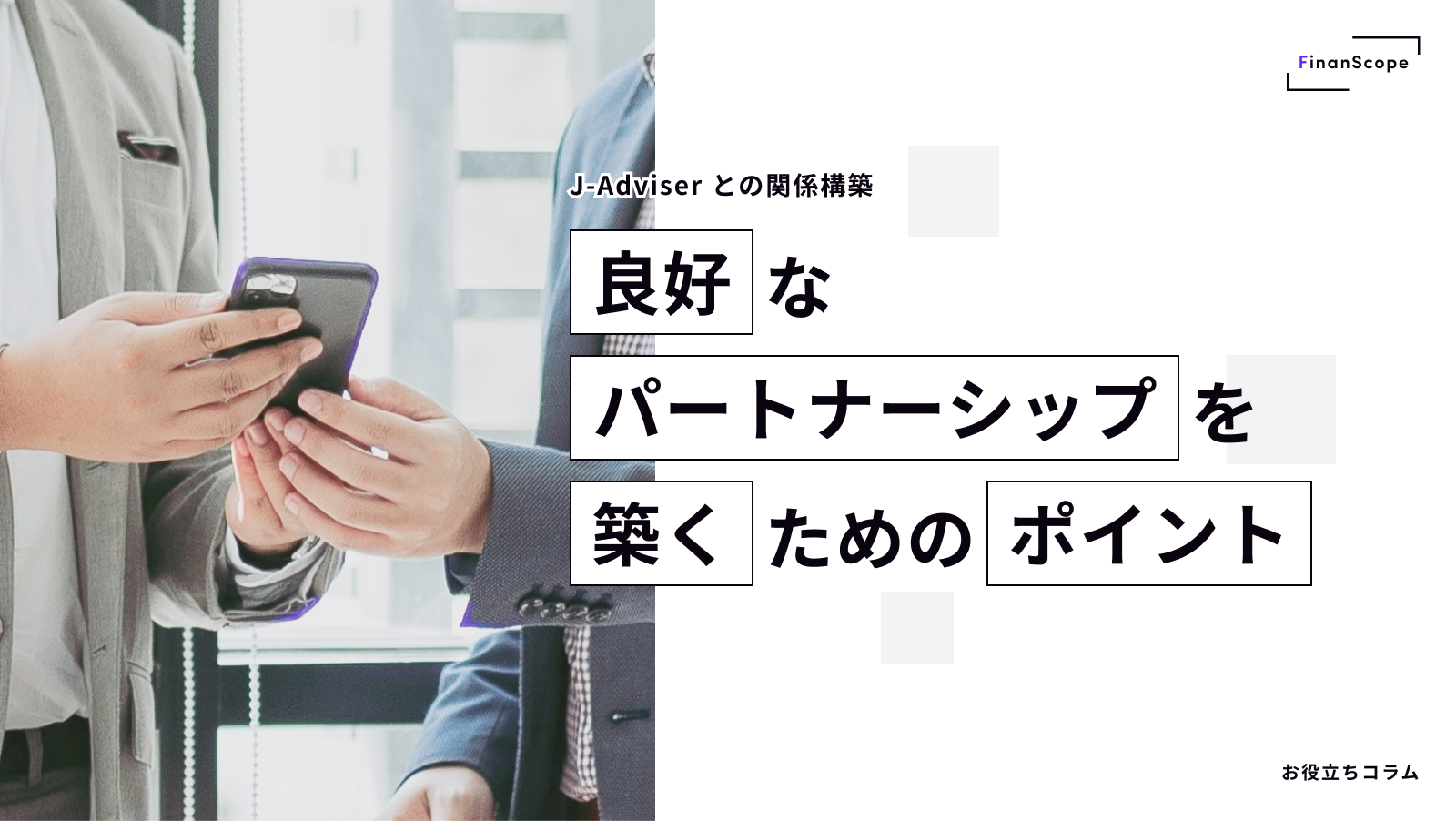
デジタルキューブ 取締役 / 公認会計士・税理士 和田 拓馬
TOKYO PRO Market(TPM)への上場を目指す企業にとって、J-Adviser との関係構築は成功への重要な鍵となります。上場審査の全プロセスを支援し、上場後もモニタリングを担うパートナーとして、J-Adviser の存在は TPM 上場において不可欠です。
私たちデジタルキューブも TPM 上場の過程で、J-Adviser との連携を通じて多くの学びを得ました。この経験と FinanScope を通じて支援してきた企業の実例をもとに、J-Adviser との効果的な関係構築のポイントをご紹介します。
目次
J-Adviser の役割と重要性
J-Adviser 制度はロンドン証券取引所の AIM 市場における「Nominated Advisers(通称Nomads)制度」を参考に導入されたもので、2008年の金融商品取引法改正によって可能となった制度です。この制度は TOKYO PRO Market のコンセプトの核となる制度であり、東京証券取引所は一定の資格要件を満たし、資格を認証した J-Adviser に対して特定業務(上場又は上場廃止に関する基準や上場適格性要件への適合調査など)を委託しています。
J-Adviser は、東証のパートナーとして TOKYO PRO Market のマーケット機能の維持向上に努めることが期待されています。また、担当会社に対して新規上場申請から上場後まで継続的に J-Adviser 契約に基づく適切な助言・指導を行う義務を負います。一般的な証券取引所への上場では証券会社が主幹事となりますが、TPM ではこの J-Adviser が中心的な役割を担います。
J-Adviser の具体的な役割
- 上場前の支援
- 上場適格性の調査・判断
- 上場申請のサポート
- 各種書類作成の支援
- 上場後のモニタリング
- 継続的な開示体制のチェック
- コンプライアンス体制の確認
- 適時開示のサポート
J-Adviser は単なる審査機関ではなく、上場に向けたプロセス全体をサポートするパートナーです。更に、流動性プロバイダーの確保支援やアナリストレポートの発行促進など、上場後も継続的に担当会社の支援を行う重要な役割を担います。彼らの知見と経験を最大限に活かすことができるかどうかが、上場準備の効率性と成功率、そして上場後の持続的成長を大きく左右します。
関係構築の3つの段階
J-Adviser との関係は、上場準備の段階によって異なる特徴を持ちます。各段階での適切なアプローチを理解することが、効果的な連携の鍵となります。
初期段階:選定と信頼関係の構築
上場準備の最初のステップは、自社に最適な J-Adviser を選定することから始まります。現在、東京証券取引所から認定を受けた J-Adviser として、証券会社やコンサルティング会社、地方銀行など、多様な特徴を持つ約20社が活動しています。このうち、実際にJ-Adviser業務を積極的に行っているのは半数程度です。複数の J-Adviser と面談し、相性や専門分野、過去の実績などを総合的に評価することが重要です。
J-Adviser 選定のポイント
- 資格と実績:J-Adviser 資格の取得要件として、コーポレート・ファイナンス助言業務に関する十分な経験を有しているか
- J-QSの体制:法令上必要な3名以上の J-QS(Qualified Specialist)が在籍し、十分な経験と知見を持っているか
- 業界知見:自社の業界に関する知識や実績があるか
- 独立性:担当会社との間に利益相反がなく、客観的な立場で助言・指導できる体制があるか
- 地域性:地方企業の場合、地理的要素も考慮すべきポイント
- コミュニケーション:担当者との相性や連絡の取りやすさ
- サポート体制:チーム構成や支援範囲の充実度
- 費用体系:上場前・上場後の費用の明確さと妥当性
J-Adviser を選定した後は、信頼関係の構築が最初の課題となります。私たちの経験では、以下のアプローチが効果的でした。
信頼関係構築のポイント
- オープンなコミュニケーション:企業の強みだけでなく、課題や懸念点も率直に共有する
- 経営方針の明確化:上場の目的や中長期的なビジョンを明確に伝える
- 初期段階での情報提供:決算書や事業計画など、基本的な資料を整理して提供する
- 課題への迅速な対応:初期診断で指摘された課題に対して、迅速かつ誠実に対応する
中期段階:上場準備の本格化と連携の深化
初期の信頼関係構築後は、実質的な上場準備が本格化します。この段階では、J-Adviser との連携もより深化し、具体的なタスクベースの連携が重要になります。
効果的な連携のポイント
- 定期的な進捗会議の設定
- 月次での進捗確認
- 重要マイルストーンの共有
- 課題の早期発見と対応策の協議
- 情報共有のルール化
- 会議体の整備(頻度、参加者、議題)
- 資料の事前共有
- 議事録の作成と共有
- 明確な役割分担
- 社内担当者と J-Adviser の責任範囲の明確化
- タスクごとの担当者と期限の設定
- 進捗状況の可視化
この段階で特に重要なのは、課題が発生した際の早期対応です。上場準備では想定外の課題が発生することは珍しくありません。そうした課題にどう対応するかが、J-Adviser との信頼関係を強化するか、あるいは損なうかの分かれ道となります。
課題対応のベストプラクティス
- 早期の報告:課題発生時には迅速に J-Adviser へ報告
- 解決策の提案:可能な限り、解決策の案を準備した上で相談
- 透明性の確保:課題の背景や経緯を隠さず共有
- フォローアップ:対応後の結果報告と再発防止策の共有
最終段階:上場審査とその先の関係
上場審査が近づくと、J-Adviser との関係はより緊密になります。この段階では、審査対応に向けた準備と、上場後の関係構築を見据えた取り組みが重要です。
上場審査に向けたポイント
- 審査資料の徹底的な準備
- J-Adviser のレビューを早めに受ける
- 指摘事項への迅速な対応
- 過去の審査事例からの学び
- 模擬面談の実施
- 想定質問への対応準備
- 説明の一貫性確保
- 経営陣の認識合わせ
- 上場後の体制整備
- 開示体制の確立
- モニタリング対応の準備
- 継続的な関係構築の基盤作り
地方企業特有の課題とその対応
地方企業が J-Adviser と連携する際には、地理的な制約がしばしば課題となります。しかし、テクノロジーの活用と計画的なアプローチにより、これらの課題を克服することが可能です。
地理的制約への対応策
- 効率的な対面ミーティングの設計
- 対面が必要な議題の集約
- 半日〜1日で複数の議題を集中的に協議
- 重要な意思決定や複雑な課題は対面で実施
- オンラインツールの効果的活用
- 定例会議はオンラインで効率的に実施
- クラウドベースのプロジェクト管理ツールの導入
- 資料の事前共有による会議の効率化
- 地域の専門家の活用
- 地元の会計事務所や法律事務所との連携
- 地域金融機関の知見の活用
- 地域ネットワークを通じた情報収集
- 連絡窓口の明確化
- J-Adviserとの連絡を担当する窓口担当者の設置
- 緊急時の連絡体制の確立
- 定期報告のルール化
当社が開発した FinanScope は、この地理的制約の克服に貢献しています。クラウドベースのプロジェクト管理により、J-Adviser との情報共有やタスク進捗の可視化が容易になります。これにより、対面での打ち合わせの頻度を必要最小限に抑えつつ、質の高いコミュニケーションを維持することが可能になるため、地方企業の上場準備における時間的・経済的コストの削減に寄与します。
J-Adviser との連携成功のための基本姿勢
J-Adviser との連携においては、以下のような点に注意すると効果的な関係構築ができると考えられます。これらは一般的な経験則から導き出されたものであり、個々の状況により適切なアプローチは異なる場合があります。
連携のための実践的アプローチ
- 定期的なコミュニケーションの確保
- 進捗状況の共有と課題の早期発見
- 明確なアジェンダと期待値の設定
- 一貫性のある情報共有
- 透明性の確保
- 課題やリスクの早期共有
- 企業の状況を正確に伝える
- 質問に対する誠実な回答
- プロアクティブな姿勢
- 課題解決に向けた自主的な取り組み
- 助言に対する迅速な対応
- 経営陣の積極的な関与
J-Adviser は上場審査において重要な役割を担いますが、同時に企業の良きパートナーとして長期的な関係を構築することが重要です。特に地方企業の場合、物理的な距離はあっても心理的な距離を縮める努力が、効果的な連携の鍵となります。
FinanScope で加速する J-Adviser との連携プロセス
J-Adviser との効果的な連携のためには、日々のコミュニケーションの質と情報共有の効率化が重要です。ここでは、FinanScope を活用した実践的なヒントを紹介します。
1. 効率的なコミュニケーション体制の構築
実践のポイント
- 定期的な進捗報告のルーティン化
- 明確なアジェンダとゴールの設定
- 課題の早期発見と共有
タスク管理と進捗共有機能
FinanScope のタスク管理機能では、J-Adviser が確認すべき重要なタスクにコメントを付し、進捗状況をリアルタイムで共有できます。これにより、対面会議の前に課題を整理し、より効率的な議論が可能になります。また、進捗会議に関しては、資料作成から実施までの時間を大幅に短縮できるため、限られた時間でより本質的な議論に集中できます。
2. 文書管理と情報共有の最適化
実践のポイント
- 重要文書の一元管理
- バージョン管理の徹底
- 必要な情報への迅速なアクセス
規程テンプレートと文書管理システム
FinanScope のドキュメント管理機能を活用すると、J-Adviser との文書共有が格段に効率化されます。40以上の規程テンプレートや上場申請に必要な文書フォーマットがあらかじめ用意されており、これらを活用することで書類作成の手戻りを大幅に削減できます。実際、テンプレート活用とチェック機能により、従来の方法と比較して文書作成の効率が向上することが期待されます。
3. 地理的制約を克服するプロジェクト管理
実践のポイント
- オンライン・対面のハイブリッド活用
- 重要な意思決定のための効果的な場の選択
- 日常的な情報共有の自動化
クラウドベース連携プラットフォーム
FinanScope は、地理的に離れた場所にいる J-Adviser とのコラボレーションを強力にサポートします。クラウドベースのプロジェクト管理機能により、物理的な距離に関わらず、タスクの進捗状況や課題を常に共有できます。これにより対面での打ち合わせを効率化し、地方企業特有の移動コストや時間的制約を軽減することが可能です。
4. 上場準備プロセスの標準化と可視化
実践のポイント
- 必要なタスクの全体像の把握
- 優先順位の明確化
- 進捗のリアルタイム把握
ガントチャートと進捗可視化機能
FinanScope の最大の特長は、上場準備に特化したタスクの標準化です。TPM 上場特有のタスクが標準で設定されており、2024年11月に追加されたガントチャート機能により、プロジェクト全体の進捗がより視覚的に把握できるようになりました。J-Adviser と共にタイムラインを確認しながら、重要なマイルストーンを管理できるため、上場準備の全体像を常に把握することが可能です。
5. 長期的なパートナーシップの構築
実践のポイント
- 成功体験の共有と振り返り
- 相互学習の姿勢
- 上場後も見据えた関係構築
上場後支援機能の拡充
上場はゴールではなく新たなスタートです。FinanScope は上場準備だけでなく、上場後の開示対応など、J-Adviser との継続的な連携をサポートする機能の拡充を進めています。特に TPM 上場企業に求められる適時開示業務などを J-Adviser と効率的に連携して行うための機能も今後強化される予定です。
これらの機能を活用した実践的アプローチにより、J-Adviser とより効果的で持続可能な連携関係を構築することができます。特に地方企業にとって、物理的な距離の制約を克服し、質の高いコミュニケーションを実現することが、上場プロジェクト成功の鍵となるでしょう。
まとめ:成功するパートナーシップの条件
J-Adviser との関係は、単なる委託先ではなく、上場という大きな目標に向けたパートナーシップです。この関係が成功するための条件を改めて整理すると、以下の3点に集約されます。
- 信頼関係の構築
- オープンなコミュニケーション
- 課題への誠実な対応
- 約束の厳守
- 効率的な連携体制
- 明確な役割分担
- 適切なツールの活用
- 定期的な振り返りと改善
- 長期的視点での関係構築
- 上場後も見据えた体制整備
- 相互の成長を促す関係
- 建設的なフィードバックの実施
J-Adviser との関係構築は、上場準備の成功だけでなく、上場後の企業としての成長にも影響を与える重要な要素です。TPM 上場を目指す企業の皆様には、ぜひこれらのポイントを参考に、効果的なパートナーシップを築いていただきたいと思います。
無料相談会のご案内
FinanScope では、上場準備に関する疑問や不安を解消するための無料オンライン相談会を実施しています。本記事でご紹介した内容以外にも、企業の状況に合わせた具体的なアドバイスを提供しています。
相談可能な内容
- J-Adviser との効果的な連携方法
- 上場準備における必要タスクの明確化と進め方
- クラウドツールを活用した上場準備の効率化
- 一般市場と TOKYO PRO Market の選択について
- FinanScope の具体的な活用方法
特徴
- 場所や時間を選ばないオンライン相談
- 上場準備の進捗状況を問わず相談可能
- 監査法人・証券会社・J-Adviser のご紹介も可能
下記ページより、相談会の予約を承っております。
URL:https://meetings.hubspot.com/takuma6/finanscope-online
一社一社の状況は異なりますが、「地方から、新しい可能性を切り拓く」。その挑戦を私たち FinanScope は全力で支援します。

上場企業とそのJ-Adviser-について解説-271x153.jpg)
-247x153.png)